学問の神様「菅原道真」とは?|天神・天満宮・牛・梅・怨霊
今回は学問の神様として有名な「菅原道真」(すがわらのみちざね)にフォーカスをあててお伝えしていきたいと思います。

菅原道真は、平安時代の貴族・学者・政治家として活躍しました。(845年~903年)
菅原道真は死後、怨霊として恐れられたと同時に多くの人に尊敬・慕われていました。
道真を神様とした、天満宮・天神社は全国に各地に広がりその数は、1万2千社あるといいます。
更に学問にも秀でた道真は学問の神様として、受験生をはじめとする合格祈願の絵馬は北野天満宮だけで毎年10万枚以上とも言われています。

受験生だけではなく多くの人に愛された菅原道真に今回は迫っていきたいと思います。
目次
菅原道真の生い立ち
菅原道真の生い立ちについて解説していきたいと思います。
神童として頭角を表す

学者家系の菅原家に生まれる
道真は父是善と婦人の伴氏の三男として生まれます。
菅原家は代々学者家系でした。
貴族とはいえ、家格としては決して高い家柄ではありませんでした。
母方の伴氏も高名な歌人を排出している家系で、大伴旅人、大伴家持らを輩出しています。 幼い頃から詩などをたしなみ、わずか5歳で和歌を読んだといいます。
5歳で和歌なんて天才児だね
学者として才能を開花させる
エリート街道を突き進む
18歳で「文章生(もんじょうしょう)」に合格します。
文章生というのは、平安時代の大学制度みたいなもので定員は20人でした。
道真はここからエリート街道を突き進んでいきます。
さらに学者としての最高位である文章博士になります。
父の他界と菅原家を継ぐ
37歳の時に父親が他界し、菅原家の私塾(山陰亭:さんいんてい)を主宰するようになります。 多くの優れた学者を排出します。
朝廷での要職をつく卒業生も出てきます。
菅原家は一大学閥となっていきます。
このあたりから学問の神様の由来がきているのかな
私塾の山陰亭は現在の、北菅大臣神社(きたかんだいじんじんじゃ)の場所にあったとされています。

- 北菅大臣天満宮
- 住所:〒600-8444
- 京都府京都市下京区菅大臣町190
このあたりの住所から菅原道真を感じることもできるね
ちなみに御祭神は道真ではなく父親に当たる是善です。
政治家としての道真
讃岐の国司として能力を発揮
道真は政治家としても才能を発揮します。
886年讃岐の国(現在の香川県)の国司として現地に赴任するのです。

国司は現在の県知事みたいなもんだね、ただ国司は1人じゃなくて複数いたけど
『菅家文草』によれば讃岐を立て直すために善政をしいて現地の民に親しまれます。
香川県には天神社(菅原道真を祀る神社)が滝宮天満宮をはじめ235社もあるといいます。*1
それほど尊敬されていたんだろうね

中央政治でも手腕を振るう

890年に京都に戻った道真は宇多天皇に抜擢されます。
891年に蔵人頭(くろうどのとう)に任じられて、蔵人頭は天皇の近臣中の近臣といえる要職であり、家格の低い菅原家から任じられるのは異例でした。
嫉妬をうむようになったのはこのあたりからね
道真は蔵人頭の職を断ってるって記録があるけど、それは許されなかったみたいだね
その後、朝廷の様々な要職について893年には参議となっています。
当時の宇多天皇の相談をする相手は、道真だったといいます。
遣唐使の廃止

894年に遣唐大使という職に任じられます。
道真としては、荒廃していた中国の唐を踏まえて遣唐使の再検討をすべきだとしています。
当時、遣唐使を送るには様々なリスクが有りました。
- 多額の費用がかかる
- 航海の危険性
まずは多額の費用がかかるということ、そして単純に危険ということもあります。
当時の航海技術はまだまだ未発達で中国にたどり着き日本に帰って来られる可能性は50%程度だったと言われています。
結果として、907年に唐が滅亡し遣唐使の歴史はここで終わります。
遣唐使の廃止によって、日本オリジナルの文化、国風文化がのちのち花開きます。
直接的では無いにしろ遣唐使の廃止に関与しているんだね
道真、右大臣になる
897年に道真は権大納言兼右近衛大将に任じられます。
藤原北家嫡流であり、道真の政敵ともいえる藤原時平も大納言兼左近衛大将になります。
朝廷は、この二人が長となり政治を行っていきます。

翌月に宇多天皇は醍醐天皇に譲位します。

譲位とは天皇の位を譲ることです。
(平成のから令和になってみたいに天皇が皇太子に天皇の位を譲ったのです。)
宇多天皇は引き続き醍醐天皇に対して菅原道真を重用するようにと求めたといいます。
899年に道真は右大臣に昇進、藤原時平が左大臣となっていたので肩を並べるようになります。
この頃も、家柄がよくない道真がここまで出世することは異例で、多くの人から妬みや中傷が増えていたといいます。
道真は何度も辞退したいと申し出ているんだけど却下されてるんだよね
出世をすることで敵が増えていったのね
道真の最後
昌泰の変
901年道真は、藤原時平の讒言(ざんげん)によって、大宰府に左遷させられます。
(京都から福岡県へ) 讒言の内容としては、
- 「宇多上皇を欺き惑わした」
- 「醍醐天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けようと謀った」
と言ったものでした。
本当に讒言したのは藤原時平か

物語やストーリーとしては、貴族の高官である藤原時平によった策謀として一般的です。
しかしながら実際のところは道真と時平は仲が良かったのではないかと言われています。
時平よりも、多くの貴族たちが道真に嫉妬して反感を持っていた朝廷の貴族・公家という説もあります。
福岡県の大宰府へ
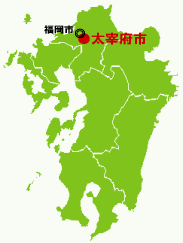
道真は大宰府へと移動しますが、その移動もすべて「自費」で、左遷先では給料・従者なども与えられませんでした。
悪質ないやがらせね
太宰府で死去
道真は、太宰府で死去します。
左遷から2年後、太宰府浄妙院で謹慎していましたが2月25日に亡くなっています。
59歳でした。
道真の子達
道真の左遷と同時に菅原道真の長男である菅原高視(すがわらのたかみ)をはじめ子供4とも流罪になってしまいます。
菅原高視は土佐(現在の高知県)に左遷させられています。
高知県には菅原高視が左遷先で道真の死を知って創建したと言われる潮江天満宮があります。

- 潮江天満宮
- 〒780-8012
- 高知県高知市天神町19−20
道真の死後
道真の死後、長男の菅原高視は許されて京都に戻っています。
藤原時平の死
908年に藤原家の藤原菅根が病死、翌年には藤原時平が39歳の若さで病死しています。
これらは道真が怨霊になって、呪い殺したのではないかとされています。
さらに右大臣となっていた源光も泥沼に沈んで溺死するとい事件も起きます。 さらに醍醐天皇の皇子である保明親王も亡くなってしまいます。
道真の復権
不幸な死が続く中、朝廷は道真を従二位大宰員外師から右大臣に戻します。
死んでるけどね

さらに930年に内裏の清涼殿に落雷が落ち藤原清貫らをはじめ多くの死傷者を出してしまいます。(清涼殿落雷事件)
これを目撃し醍醐天皇も体調を崩してしまい3ヶ月後に崩御してしまいます。
この落雷も道真の怨霊が原因ということとなっています。
めちゃくちゃ怖い怨霊だね
怨霊を鎮めるために、菅原道真を神様として、北野社に祀ります。
現在の北野天満宮です。

さらに道真の神格化は進んで、正一位太政大臣が送られます。
菅原道真は日本三大怨霊に入る
ちなみに菅原道真は日本三大怨霊としても、歴史に名前を残しています。
日本三大怨霊
- 菅原道真
- 平将門
- 崇徳天皇(崇徳院)
これだけ怨霊扱いされたらそらそうよとしか言いようがないわね
菅原道真に関わるあれこれ
歴史を踏まえて、3つのテーマをお伝えしていきます。
- 百人一首の菅原道真
- 牛と菅原道真関係
- 梅と菅原道真
百人一首の菅家

和歌、詩は大変多くの作品を残していますが、今回は百人一首をご紹介します。
小倉百人一首では、「菅家」として、下記のような歌を残しています。
「このたびは 幣も取りあへず 手向(たむけ)山 紅葉(もみぢ)の錦 神のまにまに」
小学校の時に百人一首を覚えさせられてたんだけど、「まにまに」で覚えてるわ

現代語訳
今度の旅は急なことで、道祖神授ける幣(ぬさ)も用意することができませんでした。 手向けの山の紅葉を捧げるので、神よ御心のままにお受取りください。
意味
少し、感覚的にはわかりにくいと思いますが、 旅の途中で道端の道祖神(お地蔵さんのうようなもの)にお参りするときに捧げる「幣(ぬさ)」(木綿や紙を細かく刻んだもの)を捧げるかわりに美しく色づいた紅葉を神に捧げます。
といった歌です。
手向山というのは、京都から奈良にかけての山の峠を指していると言われていますが正確な場所はわかりません。
この山と、神に捧げる「手向け」をかけているのです。
さすが、センスがいいわね
和歌三神
和歌三神に菅原道真が組み込まれることもあります。
和歌を守護する神様として、祀られており諸説があります。
- 住吉大神
- 柿本人麻呂
- 衣通姫
- 山部赤人
- 菅原道真
全然3神じゃないけどね
菅原道真と牛

天満宮や天神さまにお参りする時に「牛」をよく見かけると思います。
「撫で牛」や、牛の像などが神社にはありますが、道真と牛には様々なエピソードがあると言われています。
丑年生まれ

菅原道真が丑年(うしどし)生まれだたというこもあり、神使として道真とともに牛も神聖化されていきます。
神使(しんし)とは…(クリックで下に詳細を表示します)
神使(しんし)は、神道においての神の使いあるいは、神様の神意を代行して現世のものと接触してくれるものと考えられている特定の動物です。動物は幅広く、哺乳類・爬虫類など色々います。
元服と牛

道真が元服(大人への儀式)した夜のこと、白牛が角をくじいて死んでしまうという悪夢を見てしまい、道真はそのことを気にかけます。
自ら牛を画きお酒を備えて尊拝したといいます。
牛に命を救われる

道真が大宰府に左遷になったときに、追手(笠原宿禰ら)によって襲われてしまいます。
その際に荒れ狂った白牛が飛びて出て笠原宿禰の腹を突き刺しました。
その牛は、道真が京都で愛着を持って育てていた牛だといいます。
「この危難を助けし忠義の牛筑紫まで伴わん」と涙を流して喜んだといいます。
この牛に乗り、大宰府まで赴くことになります。 *2
動かなくなった牛

菅原道真の遺骸を載せた牛車がとあるところで座り込み動かなくなってしまったというものです。
牛が動かなくなった理由として道真はここを自分の墓所としたいのかと考えて、そこを墓地にしたそうです。
菅原道真と梅の関係

多くの天満宮、天神さまにおいて神紋が「梅」をモチーフとしたものが使われています。
飛梅(とびうめ)伝説
道真の和歌で有名なのが、百人一首の他にもあります。
それがこの歌になります。
- 東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春な忘れそ
現代語訳は
- 「梅の花よ、春風が吹いたら匂いをよこしてくれ。主人が不在でも春を忘れるな」
現在では春の花のイメージは桜でしたが、当時は中国の影響下にもあり「梅」が主流でした。
この歌は道真が京都の自宅で梅に向けて読んだ歌としていますが、道真が左遷させられたあと残された梅は春になると大宰府に飛来していったといいます。
いわゆる「飛梅伝説」というものです。
大宰府の飛梅と各地の飛梅

大宰府天満宮は九州の梅の名所となっており、約6000本の梅の木があります。
なかでも、本殿の前にある梅が、飛梅伝説で飛んできたという梅とされています。
(大宰府天満宮が建立されて、本殿前に株分けされているものです)
樹齢1000年を超える白梅で根本は3本の株からなっています。
大宰府天満宮の梅の中で一番最初に咲き始めるとされています。
また飛梅伝説は他の地方にも見られております。
- 道明寺天満宮(大阪府藤井寺市)
- 防府天満宮(山口県防府市)
北野天満宮の梅

全国の天神社の総本社として京都の北野天満宮も梅の名所として知られています。
境内には1500本の梅があり、2月から3月にかけては非公開の梅苑も公開されます。
梅ヶ枝餅

大宰府天満宮の名物として「梅ヶ枝餅(うめがえもち)」があります。
梅の味や香りがするものではありませんが、梅の焼印がしてあるお餅です。
中にあんこがあり、参道のお店などで購入することができます。
昔、パーキングエリアで食べたわ
由来としては、確かのものではありませんが大宰府の近所に住んでいた老婆が道真にお餅を梅の枝に刺してプレゼントしたことが由来とされています。
全国の天満宮
日本三天神
多くの天神さま、天満宮がありますがここでは、日本三天神をご紹介します。
また「日本三大天満宮」といったり、「日本三管廟」とと言ったりします。
天満宮は、「太宰府天満宮」と「北野天満宮」が総本社とされています。
それに加えて、日本最古の天満宮として「防府天満宮」が取り上げられることが多いです。
- 太宰府天満宮(福岡県太宰府市)
- 北野天満宮(京都市上京区)
この2社は確定的で、地域によって異なります。
- 防府天満宮(山口県防府市)
- 曽根天満宮(兵庫県高砂市)
- 和歌浦天満宮(和歌山県和歌山市)
- 大阪天満宮(大阪市北区)
- 荏柄天神社(神奈川県鎌倉市)
- 亀戸天神社(東京都江東区)
- 曽根田天満宮(福島県福島市)
- 小平潟天満宮(福島県猪苗代町)
- 大生郷天満宮 (茨城県常総市)
いつも思うけど、3大なのに3大じゃないよね
日本三躰天神
日本三躰天神というのは、道真が大宰府に左遷された際に道真自身が鏡に写して、自らを彫ったと伝わる「道真像」3体をご神体として安置する天満宮です。
「日本三体天神」ということもあります。
- 太宰府天満宮(福岡県太宰府市)
- 永谷天満宮(横浜市港南区)
- 道明寺天満宮(大阪府藤井寺市)
江戸三大天神
江戸三大天神は、江戸時代における江戸の代表的な天満宮です。
亀戸天満宮においては、江戸の外だったのでかわりに五條天神社を入れることがあります。
- 湯島天満宮(東京都文京区)
- 平河天満宮(東京都千代田区)
- 亀戸天満宮(東京都江東区)
- 五條天神社(東京都台東区)
名古屋三大天神
名古屋三大天神は愛知県名古屋市における代表的な3社の天満宮です。
三社が合同で、「名古屋三大天神参り」などの巡拝イベントなども行っています。
2020年12月に参拝してきたよ
それにしても天満宮は多いわね
まとめ
今回は、天神さま、天満宮の御祭神としての菅原道真について深堀りしてきました。
天神さまや天満宮に御朱印をいただいたり、参拝をする際は「梅の木」を探したり、「牛」に思いを寄せたりして見るといいかもしれません。

御朱印ランキング
*1: 菅原道真~信仰の里~ - 坂出市ホームページhttps://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/bunkashinkou/mitizane.html
*2:菅原道真公と牛について|長岡天満宮


